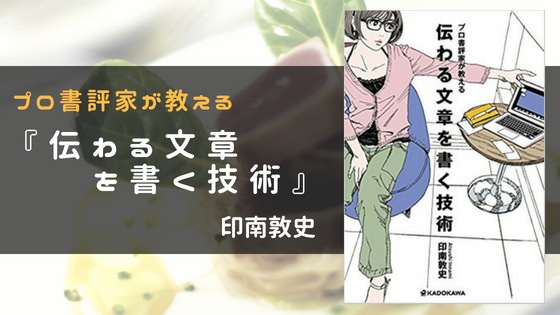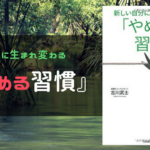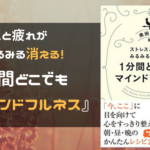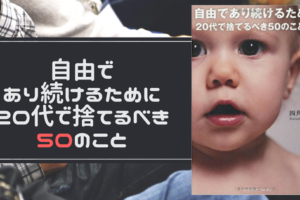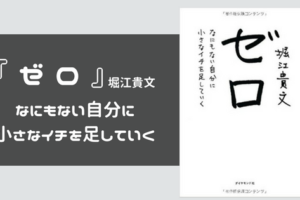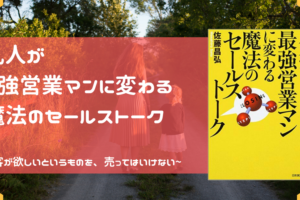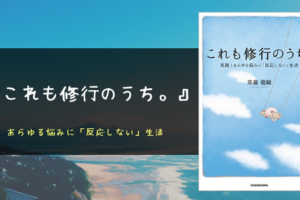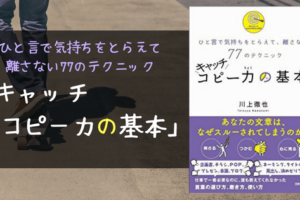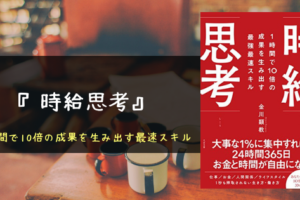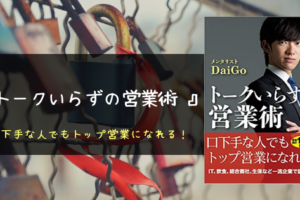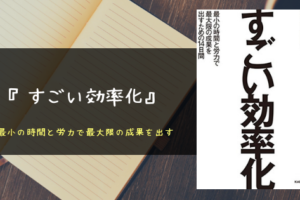最新記事 by 柿田ぴんと (全て見る)
- 【2023年】話し方、コミュニケーション能力向上のおすすめ本ランキング10冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日
- 【2023年】仕事術のおすすめ本13冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日
- 【2023年】メンタリストDaiGoのおすすめ本14冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

今日紹介するのはこちら!
『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』印南敦史
本書は、1日1冊書評を書かれている印南敦史さんの文章術本!
ぼくが書評ブログをはじめる上でかなり参考にした1冊でもあります!
今日はその中でもSTEP2の
「読み手の視点に立つ」の中から
書評ブログの書き方を「5つのポイントに分けて」紹介していきたいと思います!
☆本の内容
誰にでもできて、稼げる文章力がすぐ身につく!ビジネスパーソンのためのNo.1ブログメディアライフハッカー「日本版」の書評家が「まとめ」「書き」「伝える」テクニックを大公開!
目次
\30日間 無料体験中!/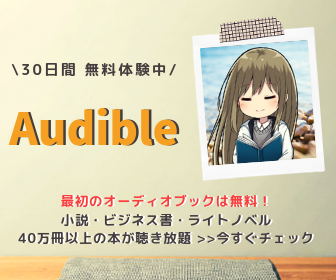 小説 ビジネス書 ライトノベル
小説 ビジネス書 ライトノベル
40万冊を「無料体験」で聴く
書評の書き方①「ターゲットを見極める」
文章には「読んでもらう」という目的が
多少なりとも存在すると思います!
感情をぶちまけた個人の日記や
めちゃんこ恥ずかしい詩を除いて!
そこで必要になってくるのが


をはっきり意識する
「ターゲット」を見極めることが大事だと本書!
本でも、企画書でも、メールでも
必ず読み手は存在するものだなと!

ってことで、本書では
意識すべき重要なこと3点を紹介しています!
②年齢
③立場
そんなの当たり前やろ!って思う人いるけど
わりとこの点を考慮している文章は少なかったり!
ぼくが思うに、読み手設定をしないってのは
真っ暗闇の中で、誰が席に座っているのか
全くわからない状態で、プレゼンをするようなもの!
あいてが小学生、または高齢者
もしかしたらアイドルかもしれない。
ラブレターも同じで
きっと読む人を想像して書くはず!
不特定多数の人に向けて書くなんて怖すぎるしな!
あいてが変われば
何を話すか、書くかも変わってくるからこそ
「ターゲット」を見極めることは大事になってくると!
書評の書き方②「目的を見極める」
次に重要なポイントは
文章を書く「目的」を見極めること!
「なにを」→どのような内容を
「どのように」→どのような手段によって
「誰に」→どのような相手に
を考えて、伝えることが大事だと!
ぼくも目的を決めることは
めちゃんこ重要だと思ってて
たとえば、料理をするときに

と言われたら、何をすればええねん!ってなるはず。
でも

と言われたら、じゃがいも、にんじん、たまねぎ
何を集めて、どの作業をすればいいか、明確になるのではないでしょうか?
つまり、目的や目標を決めれば
文章も何を書けばいいか明確になると!
書評の書き方③「読み手と時間の関係性」
ターゲットも目的も見極めて
良い文章をかけるようになったとして!
ここでは、読み手と時間の関係性について紹介!
まず知ってほしいのが、ウェブサイトの場合
ページ上の滞在時間が数十秒だったりすることは
めちゃんこよくあること!
現代人は忙しく時間をぬって情報収集していて
つまり読者は、仕事からプライベートまで
さまざまな制限に囲まれながら
記事に目を通していると考えることが重要で!
その読み手の事情を認識して
書く必要があると本書はいいます!
ちなみに著者が書評している
「ライフハッカー」の主要読者層は
25歳~34歳を中心としたビジネスパーソン!
多くは「通勤途中の電車などでスマホを利用して」
「仕事の空き時間にオフィスのパソコンで」記事を読んでいる想定だそう!
そこで著者が書評を書く上でのポイントを紹介!
そこで私の場合は、書くうえで、
「なかなか時間をとることができないビジネスパーソンが、効率的に情報収集できる」
ということを意識しました。だから私が「ライフハッカー」に書いている書評は、新聞の日曜版や週刊誌などの書評とはタイプが異なっています。
従来的な書評という概念からは外れているため、そこに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、メディアの性質や読み手の事情を考えた結果として、これがいちばん適切だと思っています。その「書き方」における重要なポイントは、「引用」 です。
一般的な書評には、引用はそれほど多くなく、その書籍の全体的な印象を俯瞰したり、評者の個人的な意見が記されているのが普通のあり方です。 しかし「ライフハッカー」の書評では、あえて多めに、その本のなかから象徴的な、もしくは印象に残った箇所を引き出すようにしているのです。
ぼくが著者の書評に興味をもったのも
引用が多くて、かつ役に立つ内容をすぐに学べると思ったから!
何よりも、読者の視点に立った場合
引用を用いたほうが具体的だし
短時間での情報収集に効果的なんすよね!
「できれば、時間をかけて読み込みたい」
「そして、そのなかから自分に必要な情報を効率的に抽出したい」
「でも現実的に、それはとても困難なこと」
というジレンマがあるからこそ、著者の書評は刺さるわけだと!
②読んだあと、ちょっと得した気分になれる
ここを意識することができれば
時間に追われるビジネスパーソンにも
受け入れられるような文章がかけるではないでしょうか!
書評の書き方④「表現する」のではなく、「伝える」
本書では書評において
1番大事にしていることがあると!
個人を立てた記事はまた別としても、一般的な情報系メディアの記事に書き手の過度な主張は必要ないと考えるべきです。
読者が求めているのは、
「仕事に役立ちそうな情報」であり、
「頭を活性化させるためのアイデア」であり、
「デスクを効率的に使う方法」などなのですから。そこに、「印南敦史が個人的になにを考えているか」はまったく必要ない。
そう考えているので、少なくとも私は、「ライフハッカー」に寄稿する原稿ではなるべく自己主張をしないように心がけています。
ぼくも書評するときは
なるべく自分の考えはいれないようにしてて!
もちろん個人の主張は、表現でもあるし
その人のオリジナリティだとは思うけども

あなたの主張に何のメリットがあるの?
って言われたら
自己満足であることも多かったり!
ぼくが思う書評ってのは
その本から読者の悩みが解決できる内容を
一貫性のある順番で抜き出す作業だと思ってて
かつ、自分が本を読んで
実践して気づいたことを
わかりやすくトッピングするみたいな!
「この本を読めば、悩みが解決できそう!」
「実践すれば、こんな未来が待ってる!」
とワクワクする記事を書きたいなと
さっそく自分の主張をしまくってるわけですが!
自分を表現するのか?情報を伝えるのか?
どっちが読者のためになるかは、難しいですが
意識して書けるようになれば、きっと
よい文章を書く事ができるとぼくは思います!
書評の書き方⑤「引用」と「地の文」のバランス
では、最後に著者が実践する
書評のテンプレートを紹介!
②引用
③解説
④引用
⑤解説
⑥まとめ
ちなみに引用の割合は
全体の3割程度にとどめるべきだと!
あれもこれも引用するのではなく
ポイントとなる部分を
フックとして活用することが大事!
その本から抜き出す引用で
その本が自分にとって必要か否か
を判断するための材料にもなるし
「自分」を表現しなくとも
「どこを引用するか」自体が書き手の個性につながるわけで!
まとめると著者が書評で大事にしてるポイントは
②紹介する書籍からの「引用」が多い
ぼくも引用で書評ブログに興味をもったように
読者は、短時間で得した情報を知りたいと!
引用しつつ、個人の表現も少しだしつつ
多くの人に役に立つ、魅力的な書評を書いていきたいですね!
書評まとめ『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』印南敦史

『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』印南敦史
いかがでしたでしょうか?
・「なかなか時間をとることができないビジネスパーソンが、効率的に情報収集できる」ことを意識する!
・短時間で得した気分にさせる!
・個人的な意見や感想を少なくする!
・紹介する書籍からの「引用」が多くする!
あらためて読んでみると
書評の原点はこの1冊だなあとしみじみ感じました(b`-ω-´)b
自分の書評にどんな価値があるのか
しっかり向き合っていきたいですね!
本書は上記以外にも
・ビジネスジャンルにおける、読み込むべき本と流し読みでいい本
・伝えるための文章表現
・「まとめるテクニック」
・「読ませる」文章の書き方
・センスを磨くためのポイント
など、プロ書評家の読書術や時間術
1日1冊ビジネス書を書評する
効率的な書き方やコツが満載となっとります!
「書評をはじめてみたい方」
「本の魅力を最大限に伝えたい方」
にはオススメの1冊なので
気になった方はぜひ本書を読んでみてくださいね!